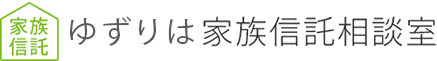自己信託と自益信託

「信託」のは3つの立場
「信託」には3つの立場が登場します。
- 財産を託す立場→「委託者」
- 財産を託される立場→「受託者」
- 財産の恩恵を受ける立場→「受益者」
信託はこの3つの立場で成り立ちますが、これらの立場はそれぞれ信託のニーズに合わせて兼用することがあります。兼用するとなると、次の3通りが考えられます。
①「委託者=受益者」
・・・自益信託と言います。
すなわち、財産を他人に託して、自分のために、管理処分してもらうカタチとなります。このカタチは一番実例が多く、信託銀行の信託商品もほとんどこのカタチです。財産の価値そのものは手元において、権限のみ移すことから、このカタチだと贈与税がかかりません。
②「委託者=受託者」
・・・自己信託と言います。
すなわち、「自己信託」は、「財産を託する人」と「託される人」が同じ、先の信託法の改正で、明文化され認められたものです。所有権の移転が伴わず、同じ人の手元に置きながら、自分の財産から信託財産(他人のために管理する財産)に変わります。よく説明の際「右手にあった財産を左手に移すことで信託財産になります。」みたいな説明をしたりすることもあります。
上記①、②の組み合わせが認められるのならば、残りの組み合わせとして、
③「受託者」=「受益者」
が考えられるかと思います。
この場合、財産の名義を取得する人と恩恵を受ける人が同じということになります。この場合が唯一、信託で認められにくいカタチです。信託の本質は、「本人のために他の者が財産管理等すること」です。
このカタチだと本人のために本人が管理することになり、そもそも普通の所有者と何ら変わりがありません。信託の意味がなくなります。しかしながら、信託法は、受託者イコール受益者になっても、すぐに信託が終了するわけではなく、1年間は猶予期間が与えられており、その間に他の人が受益者になれば、引き続き認められることになります。
見解
信託法でそのように定められていることから、信託成立当初は(1年以内に受益権を他へ譲渡する前提として)、「受託者」=「受益者」の信託も認められるとういう見解があります。
この見解に基づくことにより、上記①②③のカタチを結び付けて、信託当初は、「委託者」=「受託者」=「受益者」の信託も有効であるという見解もあります。
実際、自分の収益ビルを他へ譲渡する場合、不動産そのものを譲渡するには、高価で難しい場合がある。もっと不動産を小口化して換価していきたい場合は、そのままだと共有持分の売却になってしまう。共有の場合、物件の管理処分権が分散していまい好ましくない。
そこで、不動産を自分に信託して「受益権」という権利にした上で、不動産そのものではなく、受益権というう権利を小口化して譲渡したいというニーズがあります。そのため、いったん「委託者」=「受託者」=「受益者」として、受益者としての受益権を売却するということを前提で信託を導入するのだと思われます。この場合、受益権を売却しても不動産取得税がかからないという効果もあります。
「委託者=受託者=受益者」には問題ないのか
では、そもそも「委託者=受託者=受益者」には問題ないのか、が気になるところです。
この点、中央大学の新井誠教授など、少なくとも信託導入当初からの「委託者=受託者=受益者」については、批判的な意見が、多く見られます。理由は以下のとおり挙げられています。
- 信託法が信託として明文上認めていない、「受託者が『専ら受託者の利益』のみを図る場合」にあたるので、信託として成立しない、信託成立後に、受託者が事後的に受益権を取得してしまった場合は、例外的に1年間のみ猶予するとされているにすぎない。
- 「自分のために、自分が自分に与えた権限を行使すること」になり、これはある意味、当たり前のことであり、そもそも信託と言えないのではないか。信託の目的を設定できないのではないか。
いずれにしましても、「信託目的」を特に重視すべき家族信託の場合、家族で行われるからこそ、信託の存在、実質が問われることになります。特に「信託の目的」がきちんと維持、理解されていることが大切であることから、「委託者=受託者=受益者」の場合、信託導入時において、それに見合った信託目的が設定されているかどうかが重要であり、目的を伴わない信託については慎重にならざるを得ないと考えています。
※ちなみに、受益者が複数存在する場合で、その一部受益者が受託者である場合は、期間関係なく、認められています。