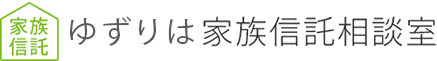【石井満コラム】家族信託の受託者による金融機関のローン借入と債務控除への影響!?

家族信託のニーズとは何か?現在、家族信託を利用した様々な提案がなされています。
将来的には複雑多様な信託へのニーズも広がる可能性があるとは思います。
ただ、目下のところでは、信託に対する典型的なニーズは、超高齢社会における認知症等による判断能力の低下・喪失リスクへの備えとしての家族信託ではないでしょうか。
いざという時に、資産が本人のために使えないという資産凍結リスクへの不安、悩みを抱える方が増えています。
これから10年、人口構造上、この家族信託へのニーズは激増することは間違いなく、社会インフラの一部として、信託の周知、普及がなされるべきであると、イチ実務家として日々強く思うところです。
家族信託を利用した借入とは?
上記ニーズを整理すると、
- 資産を有している親等(委託者兼受益者)が意図する目的と管理方法の範囲内で、
- 家族等の後継者(受託者)の権限と責任により、
- 受益者のために信託財産を適正に管理処分していくこと、
です。
そして①②③の実現のために、受託者のみの判断、契約等が実際に可能でなければなりません。典型例として、信託された財産を利用した借入・担保提供の実現があります。そもそも、金融機関からの借入もできる内容でなければ、家族信託のニーズに応えているとは言えないのではないでしょうか。
ここで大切なポイントですが、この借入とは、あくまでも「受託者」による借入のことであるべきです。
意外とこの受託者でローン契約を行うことについて、未だに消極的な提案をされているケースを耳にいたします。 将来の相続税の申告を考えて委託者(受益者)を債務者としたという話も聞きます。受託者借入への不安はまだまだ小さくないのかもしれません。
ただ、家族信託が上記ニーズに応えるためには、借入も受託者により実現できなければ意味がありません。委託者の意図は、受託者による財産管理処分の実現にあるはずです。家族信託を利用した借入とは、あくまでも「受託者」による借入が基本にならなければなりません。
受託者による借入に、法的根拠はある?
受託者による借入は法的に危険なのか?
本来、全くそんなことはないはずです。
そもそも受託者による借入は、信託法第21条第1項5号に該当します。条文には、「信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利、に係る債務」とあります。そしてこの債務は、信託財産責任負担債務になります。逆に言うと、委託者から託された財産を責任財産として借入をするためには、受託者による借入を行わなければならないのです。
もし、委託者で借入をしてしまうと、委託者名義の資産は責任財産となりますが、信託して名義を移転した財産は責任財産になりません。担保不動産は影響ありませんが、信託財産が収益物件であった場合、収益金の口座は責任対象でないことになります。
受託者により信託財産責任負担債務とすることで、信託財産と債務を受託者により管理することができ、受益者の有する受益権の価値も、信託に含まれる財産と債務による価値になります。
さらに将来の受益者の相続時には、信託財産に属する資産と負債の遺贈を受けたものとして相続税法の適用が想定されます(相続税法第9条の2)。
信託財産責任負担債務ってどんなもの?
ここで、少し悩ましいのは、信託財産責任負担債務の契約当事者はあくまでも受託者であることから、受託者自身が債務者であり、この債務については、受託者自身も、その固有の財産をもって無限の責任を負うことです。
しかしながら、この債務はあくまでも信託財産で負担する債務です。もし受託者で支払いをした場合は、受託者は信託財産から当然に償還を受けられるものです(信託法第48条)。例えるならば、受託者は信託財産(受益者の財産)の連帯保証的な立場とも言えます。
税務的には、「確実な債務」は誰が負担するかが重要であるかと思いますが、あくまでも信託財産で負担する債務であるところが「信託財産責任負担債務」たる所以であり、債務の負担者は、まずは信託財産すなわち実質的には受益権を有する受益者です。
なお、受託者による借入を実現するための留意点としては、
- 信託契約上、信託目的及び受託者の権限に沿った適正な借入行為であること
- 金融機関のリスクを考慮した金融機関の理解を得られる信託内容であること
- 過剰融資または信託財産だけでなく受託者の信用力を利用した借入になっていないこと
- 信託の終了時を想定した出口を見据えていること
- 借入契約の締結の仕方
などです。
委託者兼受益者が亡くなって終了する信託は危ない??
昨今、委託者兼受益者の生前の財産管理処分を目的とする信託で、かつ、委託者兼受益者が死亡したらその目的を達する内容にも拘わらず、受託者借入を想定する場合は、死亡しても信託を終了させず、数日、または数カ月存続させてから終了させるという内容の契約を拝見することがあります。
事情を聞くと相続税申告における債務控除の適用を確実に受けるためには、このような内容でなければ危ないということです。根拠として相続税法第9条の2の条文の定め方によるとのことです。すなわち、同条6項(相続税法上、資産と負債を承継したとみなす)に同条4項(終了による帰属権利者による取得)が含まれていないとのことです。
委託者兼受益者が死亡しても信託が存続していると同条2項(終了しないで次の受益者による取得)が適用され債務控除の適用に問題ないが、信託を終了させると、同条4項が適用され6項から外れるため債務控除の適用が危ない、とのことです。
この主張どおりだと、委託者兼受益者の死亡により信託終了とし帰属権利者に財産帰属するという最もシンプルな内容だと債務控除が危なくて、死亡後も無理やり存続(しかも短期)させると債務控除は大丈夫とのこととなります。
なるほど、条文を見ると一見、説得力があるようにも見えます。
しかしながら、、、
信託実務家として叫びたい!
そもそも、信託は信託法上、目的を達成すると終了します。
亡しても存続させたいならば、死亡しても存続するに足る信託目的が前提です。当然、債務控除の確実な適用は信託目的になり得ません。目的達成したら、死亡により信託期間を終わらせないようにしていても信託は終了します。
一方、家族信託へのニーズとして、生前の管理のみ(死後の事務まで求めない)の場合も多く、それらは債務控除が危ないということでしょうか?
そもそも税法はそのようなものなのでしょうか。
私は税務の専門家ではないため、税務について責任のある提案をできる立場にはありません。ただ、信託の実務家として、信託しても税務上不利益なく公平に適用されることを願うばかりです。
単なる条文の上っ面で判断するのではなく、その条文の深い読み込み、実体法と税法のつながり(少なくとも実体法及びその解釈あっての税法のはずです。)、を強く意識するべきではないでしょうか。その意味で、確かに相続税法9条の2の4項は6項に含まれていませんが、そもそも4項には「残余財産」とあります。残余とは清算後の残余、すなわち債務を処理した後の財産という意味です。であるならば、この「債務」はどこに行くのでしょうか?
6項に4項が含まれていないのは、おそらく信託法181条を前提にしていると思われます。信託法181条は残余財産の給付は債務を弁済した後でなければできないと定めています。これを受けると9条の2の6項に4項が含まれないのはある意味当然です。4項のケースでは債務が残存することが明文(信託法181条)では想定されていないからです。
ここで信託法の解釈上論点があります。181条は強行規定か任意規定かです。立法担当者、通説的立場(道垣内弘人教授 信託法 有斐閣等)、旧法時代からの実務例(土地信託)は全て任意規定を前提としています。自ずと債務が残存している場合も想定しなければなりません。

そもそも、信託は終了しても直ぐに消滅するわけではありません。終了しても清算する必要があります。死亡により信託終了しても帰属権利者に渡るまでは、ある意味信託状態が続くのです。このことは信託法176条により清算結了するまでは信託は存続するとみなすと明文で定めています。
では、この間は受益者の存在は空白になるのか?
いえいえ、信託法183条6項で、この間は帰属権利者は受益者とみなすと定めています。
委託者兼受益者死亡により信託終了して受益者とみなされた帰属権利者が取得する信託存続中の資産と負債は遺贈で承継したとみなされないのでしょうか?
4項の「残余財産」の意味は?
9条の2項の適用は本当に無理なのか?
もっと深く実務家は議論しなければなりません。少なくとも私は、本質から外れる小手先のみの信託には到底、賛同できません。このような事例が既成事実化していくことに大きな不安を感じています。なぜならば、ニーズ゙に適した分かりやすい内容が家族信託には何より求められるからです。
家族信託が社会インフラとして普及するためにも、ニーズに合わせた実体法であり、そのための税務や登記であることを再認識しなければならないと思っています。
自戒を込めて。。。